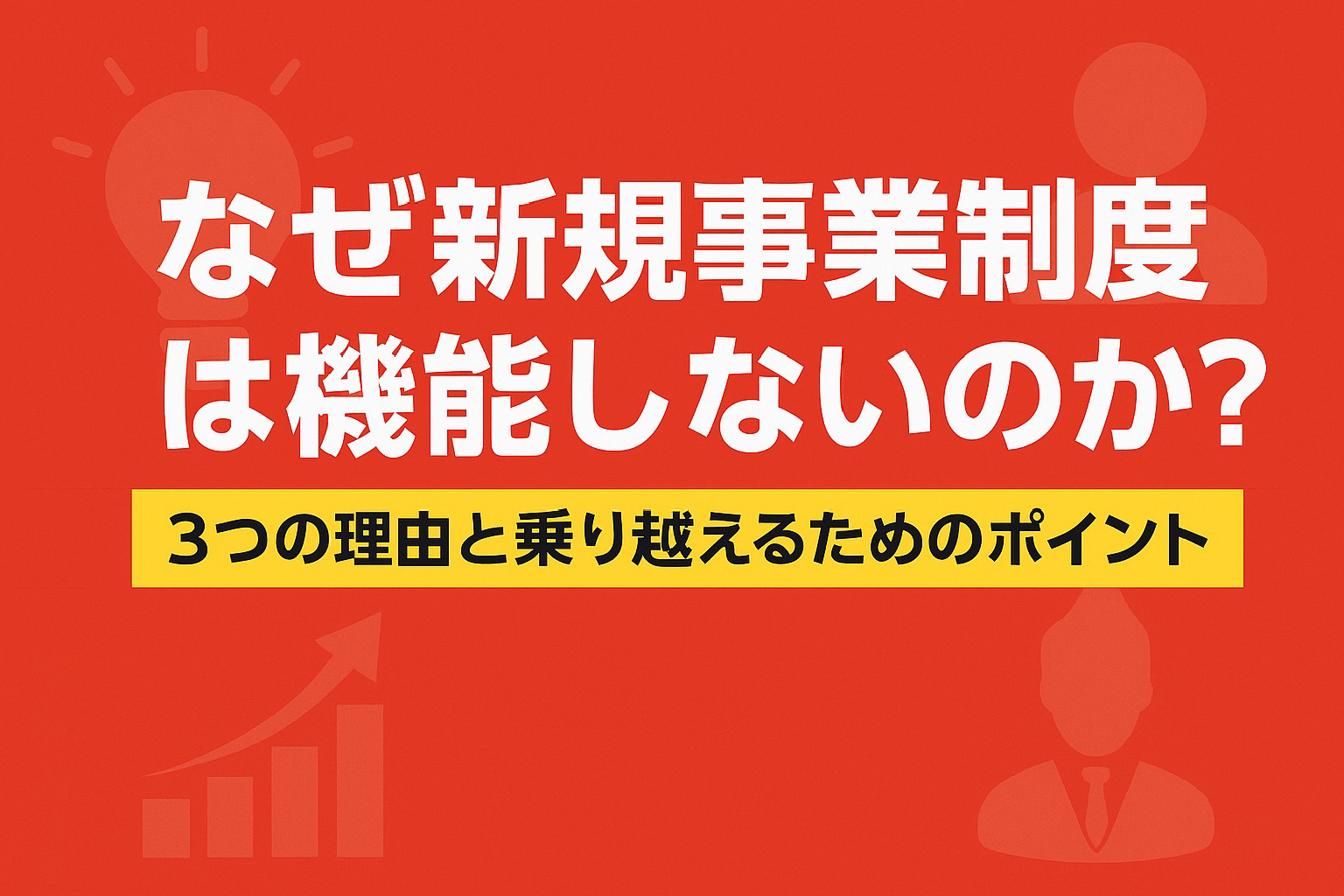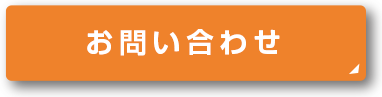この記事はこんな人におすすめ!
・ 社内新規事業制度を導入したものの、なかなか成果が出ないと感じている経営層や企画部門の方
・「手を挙げる社員が少ない」「制度が形骸化している」といった課題に直面している人事・制度設計担当者
・ 新規事業に挑戦したいが、評価やリソース不足に悩む現場マネージャーや社員
・ 組織にイノベーション文化を根付かせたい経営企画・事業開発リーダー

多くの企業で社内新規事業制度は導入されているものの、成果が出ずに形骸化してしまうケースが少なくありません。その主な理由は、①既存業務が優先される構造、②成果が評価に反映されない仕組み、③モチベーションが続かない環境の3点です。
これを乗り越えるには、新規事業活動そのものを評価制度に組み込み、定量(提案件数・検証回数など)と定性(学びの質・チームへの影響など)の両面で挑戦を正しく評価し、さらに専任リソースや時間を確保する仕組みが不可欠です。
例えばGoogleの「20%文化」に代表されるように、社員が業務時間の一部を新規アイデアに充てられる環境を整えることで、制度は「存在するだけの仕組み」から「成果と学びを生み出す仕組み」へと進化します。その結果、社員が安心して挑戦できる文化が根づき、イノベーションが継続的に生まれる組織へと変わると考えられます。

「社内新規事業を制度化したのに、なかなか成果が出ない…」
「手を挙げる人材が限られ、進行も思うように軌道に乗らない…」
こうした声は、多くの企業で共通する悩みです。制度そのものは整えても、実際には社員の挑戦が広がらず、“絵に描いた餅”に終わってしまうケースが少なくありません。
背景には、兼任社員の負担・人事評価の不整合・モチベーション維持の難しさといった、どの企業でも直面しやすい構造的課題があります。
本記事では、新規事業制度が機能しない3つの理由と、それを克服するための3つの改善ポイントについて具体例を交えて解説します。
社内新規事業が進まない3つの理由
理由① 既存業務が優先される構造
新規事業は成果が出るまでに時間がかかり、売上貢献も不透明です。一方で既存事業は短期的に成果が見えやすく、評価も明確。そのため、兼任で新規事業を任された社員は自然と既存業務を優先してしまいます。
想定される失敗例:
ある製造業のA社では、新規事業提案制度を設けたものの、提案した社員が日常業務に追われて動けず、結局計画倒れに。経営層が「本当にやる気があるのか」と疑念を抱く結果となりました。
理由② 成果が評価に反映されない
従来の評価制度は既存事業に重きが置かれ、新規事業の取り組みは「成果なし」と見なされがちです。むしろ既存業務の成果が下がるとマイナス評価になるケースもあります。
社員の本音:
「提案しても昇進や給与につながらないなら、わざわざリスクを取る必要はない」
理由③ モチベーションが続かず制度が形骸化する
最初は制度に関心を持つ社員が集まっても、成果が認められなければ次第に熱が冷めます。結果的に「制度はあるが誰も使わない」状態に陥り、制度そのものが形骸化します。
想定される失敗例:
大手小売B社では、初年度に50件以上のアイデアが出たものの、翌年以降は数件に激減。理由は「評価に結びつかない」「業務量が増えるだけ」という社員の声でした。

改善に向けた3つのポイント
ポイント① 新規事業活動を評価に組み込む
新規事業は短期的な売上や利益よりも、挑戦そのものに価値がある活動です。そのため、評価制度の中に「挑戦を数値化して認める仕組み」を明確に組み込む必要があります。
評価指標の具体例:
・アイデアの提出数(数の多さを評価することで、まずは発想を促進)
・PoC(実証実験)の実施件数(小さく試す文化を根づかせる)
・学びや失敗の共有回数(失敗を組織全体の資産とする)
たとえば「年2回以上の提案をした社員はプラス評価」「学びの発表をした社員は昇格条件に加点」といった仕組みを導入すれば、社員は安心して新しい試みに挑戦できます。
こうした評価の明示は、「制度があるけれど評価されない」という不信感を払拭し、社員が手を挙げやすい環境を作り出します。
ポイント② 定量と定性の両面から評価する
新規事業は結果が出るまでに時間がかかるため、数値的な成果だけでは努力を測りきれません。そこで、定量+定性の両面で評価することが重要です。
・定量評価:提案件数、検証回数、協力したメンバー数など
・定性評価:学びの質、チームへの貢献度、社内外への波及効果など
これにより「目に見える成果が出なかった挑戦」も正しく評価できます。
他社事例:
海外のテック企業では、プロジェクト終了時に「成功要因」「失敗要因」「次に活かせる3つの学び」を必ずまとめて提出する取り組みが見受けられます。これは成功・失敗にかかわらず報告の内容が評価に直結します。これにより失敗が単なるマイナスではなく、組織の次の成功への投資として扱われています。
結果として社員は「数字が出なくても努力が認められる」安心感を持ち、次の挑戦に向かいやすくなります。
ポイント③ 専任リソースを一部確保する
新規事業をすべて兼任で進めるのは限界があります。日常業務の合間に取り組むだけでは、どうしても後回しになりがちです。そのため、少数でも専任人材や専用の時間を設けることが不可欠です。
・専任人材の配置:新規事業専任チームを少数でも置く
・時間の確保:週1日や月数日を「新規事業に専念する日」と定める
・外部リソースの活用:外部の専門家やアドバイザーを巻き込み、社内人材を補完する
他社事例1(国内企業):
ある大手メーカーでは「週1日新規事業デー」を導入。普段は営業や開発を担当する社員も、この日は業務から切り離されて新規事業に集中できるようにしました。その結果、年間で複数のPoCが立ち上がり、うち2件は実際に事業化に成功しました。
他社事例2(Googleの20%文化):
Googleは社員が勤務時間の20%を自分の関心ある新規アイデアに使える仕組みを導入していました。この取り組みから、GmailやGoogleマップといった世界的なサービスが生まれています。
重要なのは、単に「余暇で取り組む」ではなく、制度として業務の一部を新規事業に充てる仕組みを整えた点です。これにより、社員は心理的な後ろめたさなく挑戦でき、企業としても新しい成長の芽を継続的に得ることができました。
こうした仕組みを設けることで、新規事業は「片手間の活動」から「本気で取り組むテーマ」へと格上げされ、組織全体のイノベーション力を高めることにつながります。

期待できる成果
1.挑戦しやすい環境の整備
「リスク」から「正当に評価される活動」へと意識が変わり、社員が安心してアイデアを出せるようになる。
2.制度の実効性向上
提案件数・実行数が増え、制度が“動く仕組み”へと変化。複数のプロジェクトが並行することで、企業の成長ポートフォリオが広がる。
3.組織学習の蓄積
失敗事例や検証結果が共有され、次の挑戦に活かされます。知見が「属人的」ではなく「組織資産」として残る。
4.イノベーション文化の醸成
「挑戦は報われる」という文化が根づき、社員が自発的に動き出す好循環が生まれる。
5.経営戦略との接続強化
学びがレポートとして蓄積されることで、経営層が新たな投資判断を下しやすくなる。結果的に、新規事業制度が「戦略を進める仕組み」として位置付けられる。

まとめ
・新規事業制度が機能しない理由は、既存業務優先/成果が評価されない/モチベーションが続かない
・乗り越えるためのポイントは、挑戦を評価に組み込む/定量と定性で多面的に評価/専任リソースを確保
・成果としては、挑戦文化・制度の実効性・組織学習・イノベーション醸成・戦略接続が期待できる制度設計そのものよりも、社員が挑戦を続けられる環境づくりこそが経営層に求められる視点です。